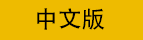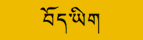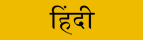デ・ソト氏はまず、「なぜこれほど多くの人々がこれほど少ししか持っておらず、これほど少しの人々がこれほど多くを持っているのか」を考えることから始めるとよいのではないか、と提案した。ベルリンの壁が崩壊したあと、自由な市場を基盤とする資本主義が勝利したとデ・ソト氏は述べ、剰余価値の可能性を生む資本は経済発展に必要不可欠であると説明した。彼は、資本主義は契約と資産文書に依存して成立するという考え方を紹介し、契約と法律に基づいて所有する資産を一切持たない人は世界人口の7割もいると語った。こうした状況は、「世界とは何か?」という質問に対して、「すべてのものは相互関係を持っている」と述べたウィトゲンシュタインの言葉を連想させるものである。とデ・ソト氏は述べた。
自由な企業の活動はインドの発展にどのように寄与したかという質問に対し、ヴィシュヌ・スワミナサン氏はデ・ソト氏が資産について述べたことを引き継いで、インド人の97%は所得税を収めていないという事実を語った。そのため、こうした人々は社会システムの中に入れず、住宅ローンを組めず、通常の方法では不動産も購入できないと説明した。スワミナサン氏とその共同経営者たちは、こうした人々と建設業者をつなげる必要性を感じ、そこで女性の果たす大きな役割を見出した。月々の諸費用の支払いを担っているのは女性であり、コミュニティの人々をつないでいるのも女性である。また、スワミナサン氏とその共同経営者たちは、たとえ貧しい人々であっても希望と目標を持っていることを知った。女性たちは、たとえ冷蔵庫がなくても、新しい家には自分一人の空間が欲しいとはっきり表明したのである。
世界経済の利潤は一貫して拡大し続けているが、その分配は依然として不公平なままである、とシヴ・ケムカ氏は指摘した。富の分配が不公平な状態は、熱く焼けたプラットホームの上に立っているようなものだと彼は述べた。ガーチャラン・ダース氏はこれには反対で、自分の運転手はこうした考え方はしていないと述べた。
 |
| AEIシンポジウム2日目の第1セッションで話をするシヴ・ケムカ氏。2015年11月5日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁) |
そして、「私の運転手は、大富豪のムケーシュ・アンバーニ氏が金持ちかどうかなど気にしていません。彼が気にしているのは娘を学校に行かせたいということだけなのです。インドでは平等よりも貧困からの脱却の方が重要です。嫉妬の問題ではないのです」と述べた。
シヴ・ケムカ氏はこれに反論した。「私が問題にしたいのは機会の平等であり、草の根から富を生んでいけるかどうかという点です。社会のシステムはうまく機能していると思えません。社会の仕組みは腐敗した八百長試合のようで根底にあるべき道徳が欠けています。マーティン・ルーサー・キング牧師は、『人は誰でも、創造的な利他主義という光の道を歩むのか、それとも、破壊的な利己主義という闇の道を歩むのかを決断しなければならない』」と述べました。これはとても力強い考え方です。
サダナンド・デューム氏はジェイ・パンダ氏に、パンダ氏の選挙区の有権者たちなら何と言うだろうかと尋ねた。パンダ氏は、「一般的には、有権者たちはダース氏が述べたように子供の教育や病院施設の改善などに関心を寄せている」と答えた。とはいえ、社会システムの腐敗があまりにひどくなれば人々の怒りは爆発するだろうと述べ、昨年のインドの総選挙の結果は、単にモディ派の勝利でなく、腐敗とインフレに反対する勢力の勝利だったと示唆した。
意見を求められた法王は次のように答えられた。
「私にはよくわかりません。こういった問題は大変複雑であり、全ては互いに関係し合っています。私たちがまだ触れていない点は、アメリカの成功がどれだけ戦争と関わりがあるか、つまり武器の製造と販売によるものかということです。そこに循環はありません」
「資本主義は主に利潤が原動力となっているようですが、社会主義は少なくとも社会全体のことを考えているように私には思われます。マルクスの言葉で私が興味深く感じているのは、労働者が搾取されていることを懸念すべき状態と捉えて、より平等な富の分配を唱えた点です。資本主義と社会主義はいずれも、それに参加する個人が作っていくものです」

|
AEIシンポジウム2日目の第1セッションでお話をされるダライ・ラマ法王。2015年11月5日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
「思いやりは道徳の基本です。よい行動になるかどうかは、行為自体によって決まるのではなく、それが他者と他者の権利に対する思いやりから生まれたものかどうかによって決まります。これが道徳的な考え方の基本です。他者に対する思いやりを若い世代の人々の心に浸透させ、やさしさと思いやりを大切にする教育をしていけば、今以上に信頼と思いやりに満ちたよりよい世界を築くことができるでしょう。こうした複雑な問題に対しては、私にはこれ以外に答えようがありません。今、私たちには自分の心の持ちかたを変えていくことが求められています」
デューメ氏は、法王がインドに亡命されてから約57年が経ちますが、物事はよい方向に変化しているでしょうか、と法王にお尋ねした。
法王は次のように答えられた。「もちろんです。インドには古代からアヒンサー(非暴力)という思想があります。他人から搾取する機会があっても、それを行使せず自制するのがアヒンサーであり、これはカルーナ(慈悲の心、あるいは他者への敬意)から生まれます。もし悪い動機を持ってすれば、たとえよい行ないであってもそれがよい結果を生むことにはなりません。民主主義はよいものですが、それに関わる人たちが利己的な考え方をしていれば、本来のよさを発揮することはできませんし、もし自由がなく、言論にも制約が加えられていれば、創造性を十分に発揮することもできません。そこで、私は中国の人たちに会うたびに、13億人の中国人は現実に何が起こっているのかを知らされるべきだと言っているのです。そうすれば、中国の人たちは善悪を判断する力を培うことができるでしょう。検閲は間違っています。この点において、インドははるかに自由な国です。現実的な人間になりたければ、現在の状況に基づいて行動しなければなりません」
「資本主義がよいか、それとも社会主義がよいかという問題についてですが、ソ連が崩壊して東欧諸国にその影響が及んだ後、私はチェコスロバキアのハベル大統領から招待を受けました。私はハベル大統領に、こうした歴史の分岐点にあっては、資本主義、社会主義の両方の長所を取り入れるのがよいだろうと提案しました」
短い休憩時間の後、ロバート・ドーア氏を司会進行役として第2セッションが始まり、法王とガーチャラン・ダース氏、アーサー・ブルックス所長、タリー・フリードマン氏(フリードマン・フライシャー・アンド・ローの会長兼最高経営責任者)の間で討論が行われた。第2セッションのテーマは「市場は倫理的か?」というものであった。

|
AEIシンポジウム2日目の第2セッションでダライ・ラマ法王とともに話をするガーチャラン・ダース氏。2015年11月5日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
ガーチャラン・ダース氏は、市場は道徳的でも非道徳的でもなく、行動のためのシグナルを与えるものだと述べた。ダース氏は自宅付近の果物売りの女性を例に挙げた。ダース氏が彼女の売るマンゴーの値段が高いと文句を言ったところ、彼女は、「でもとっても美味しいんですよ」と言った。そこで彼はマンゴーを買ったが、まずかった。ダース氏がそのことを友人や隣人に話したところ、彼らは彼女の商売敵からマンゴーを買うようになった。ダース氏は、こうしたことが、悪しき行動を罰する選択と能力を行使するということだと説明した。彼女のように不正直な人はこのように買い手の信頼を裏切るが、市場のメカニズムのおかげで、人々に受けいれられる行動が強化されるのだと述べた。
ダース氏はさらに、2つの例を挙げた。ダース氏がプロクター・アンド・ギャンブルに勤めていた時、仕入れ担当者が業者の提示価格を値切ったことから質の劣った部品が供給されるようになった、というのが悪い例である。一方で、ある小規模企業ではいつも最高の人材を採用することが可能であり、それは従業員の待遇がよいという評判が立ったためである、というのがよい例であった。
「市場は信頼に基づいて成立しています。タクシーに乗るとき、運転手は私が十分なお金を持っているかどうかを調べたりはしません。客を信頼するのです。市場はシグナルを発し、その結果として生じる自己規制が、経済を作っていくのです」とダース氏は述べた。
アーサー・ブルックス所長は、よい資本主義にはサービス、執着を離れること、楽観主義という基本的な価値観が織り込まれていると主張した。サービスとは思いやりのことである、とブルック氏は定義し、自由な企業は慈善ではなく、機会を作り出すことで卓越した存在になる、と述べた。そして、執着を離れるとは、物質主義の持つ力とその危険を理解することだと述べた。ブルックス所長は、毛沢東はよい考えを出発点としていたが、権力を得て腐敗したと述べたチベット人僧侶との会話を引用した。ブルックス所長は、私たちは他者を助けるための資源を管理する者であり、私有財産制は物を保護して他者と分かち合うためのメカニズムだと述べた。彼は同僚に対して感謝を忘れないようにと助言しているそうである。第3の価値観である楽観主義は、他者に対する信頼を維持することだとブルックス所長は述べた。つまり、貧しい人たちのことを問題と見なすのではなく、将来への潜在的な資産と見なすこと、そして、貧しい人たちもまた可能性を持っていることを認識する、ということである。

|
AEIシンポジウム2日目の第2セッションで意見を述べるリビー・リュー氏。2015年11月5日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
ラジオ・フリー・アジア代表のリビー・リュー氏は、道徳的資本主義に対するアメリカ人の関心の高さと中国の状況を比較した。リュー氏は中国の巨大な影響力を認めた上で、道徳的な中核の欠如、スピリチュアルな生活や共同体感覚の欠如に対する不安を吐露した。中国の資本主義はエリートが管理するトップダウンのものであり、中国で善き行ないをしようとする者は腐敗によって妨害されている、と述べた。リュー氏は、人間の善き精神は最終的には勝利するだろうと述べ、明るい調子で話を締めくくった。
タリー・フリードマン氏は、こうした資本主義を称える議論に警鐘を鳴らした。米国では経済のユートピア・モデルはほぼ絶滅したが、「縁故資本主義」の失敗に見られるように、資本主義は失敗するときがあると述べた。しかしながら、自由な資本主義の成功は科学によってもたらされたとして、よき行動に報酬が与えられることで、資本主義のプラスの価値は最大化されうる、と述べた。
ガーチャラン・ダース氏は、自己利益は正当であり、単なる強欲ではないと述べた。エルナンド・デ・ソト氏はアラブの春が世界中の注目を集めたのはそれが純粋な草の根運動だったからである、と述べた。人々は、政府によってあらゆる価値が奪われるのはもう沢山だという気持ちになっていたのである。ダニエル・プレッカ氏は、アメリカは経済面で最も成功している世界最大の強国だと宣言し、アメリカ政府がその道徳的権威の行使をためらうとき、アメリカにとっての試練が訪れるだろうと述べた。
ロバート・ドーア氏が法王にインドの資本主義について尋ねると、法王は次のように答えられた。

|
AEI シンポジウム2日目の第2セッションでお話をされるダライ・ラマ法王。2015年11月5日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
「インドにはアヒンサー(非暴力)という古代からの基本的な価値観と、異なる宗教間の調和があると私は常に語り続けてきました。こうした価値観は今でも守られています。また、インドには、古代から引き継がれてきた高度に発達した知識体系としての哲学があります。これらはインドの財産の一部です。現代を生きるインド人は近代教育を受けて、技術的な発展を追求していますが、だからといって、こうした歴史の試練を経た思想が軽視されるべきではありません」
「私にひとつ質問をさせて下さい。スウェーデンは貧富の差が少ない、真の意味での社会主義国のように見えます。オーストリアも同様に、億万長者は少ないものの、やはり貧富の格差がそれほど大きくないようです。これは何故だと思いますか?」
法王のご質問に対し、アーサー・ブルックス所長は、そのような事実がより明らかに見られるのはデンマークであるとして、その理由は、人口の少ない小国であり、国民の意見が比較的容易に一致しやすいからである、と述べた。ブルックス所長は、しかし、デンマーク型モデルはインドにはあてはまらないのではないかと述べた。エルナンド・デ・ソト氏もこれに同意し、米国はこうした問題に対処する方法の一つとして、一つの党は大企業から人々を守ることに力を注ぎ、他の党は大きな政府から人々を守ることに集中していると述べた。
 |
| ダライ・ラマ法王公邸で行われたAEIシンポジウムの第2セッションで意見を述べるアーサー・ブルックスAEI所長。2015年11月5日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁) |
そして法王は、次のように述べられた。「私がここで強調したいのは、宗教的な信仰ではなく、人間の根幹を成す善良さです。人間が生き残っているのは思いやりと基本的な愛情のおかげです。愛情に包まれて成長した子供は健全に成長します。様々な時代、場所、状況において、すべての宗教が愛の必要性を強調したのは、人間の生存は愛に依存しているからです。純粋で真の愛情は私たちすべての人間関係にプラスに作用します。ストレスと恐れは私たちの健康を害しますが、穏やかな心は健康を維持し、促進すると科学者も述べています」
「思いやりを持つことは私の膝の痛みにはあまり役立ちませんが、私の全般的な幸福感には多いに役立っています。あたたかい心は人間が生き残る鍵となる大切なものです。もし経済が他者を思いやる心を原動力とするようになれば、物事は今とは違ってくるでしょう。私たちはそのような取り組みを始めなければなりません。そしてこの視点から言えば、世界にとって重要なのがアメリカ経済です」
シンポジウムを総括して、ブルックス所長は聴衆に向かって次のように締めくくった。
「4つのことを是非実行しましょう。豊かさに感謝する、欲張りな心を捨てる、機会を生むために努力する、そしてここで話し合い、行われたことを世界に発信し拡げていくのです。ダライ・ラマ法王、ご臨席いただきどうもありがとうございました。ご一緒できたことを大変光栄に思います」