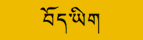ダライ・ラマ14世 テンジン・ギャツォ
以下は、2005年11月12日にワシントンDCで開催された神経科学学会の年次総会でダライ・ラマ法王が行なわれた講演に基づいてまとめられた。
この数十年の飛躍的な進歩は、人間の脳と人間のからだをひとつの全体として科学的に理解するようになったことです。さらには新たな遺伝学の出現にともない、神経科学者たちの知識は、生物有機体の仕組みについて個々の遺伝子を最も微細なレベルで理解するまでに到りました。その結果、生命の暗号そのものを操作するという思いもよらない技術が生まれ、人類全体にとって完全に新しい現実が創り出されようとしています。こんにち、科学と人類社会との接点にあるのは、もはや学術的な問題だけではありません。人類の存亡にかかわる緊急課題として取り組まねばならない問題なのです。ゆえに私は、神経科学と社会の対話は、人間であるとはどういうことか、人間として私たちが他の有情と分かち合っている責任とは何であるか、自然界にたいする責任とは何であるか、という基本的な理解を深めるのに役立つ可能性があると考えています。私は、この幅広い接点のひとつとして、一部の神経科学者たちの間で、仏教徒の瞑想修行者と奥深い対話をすることにたいする関心が高まっていることを嬉しく思っています。
私自身、科学に興味を持つようになったのは、飽くなき好奇心を抱いていた少年の頃、チベットでのことでした。それから徐々に、現代社会においては科学技術が大変重要であることを理解するようになりました。そこで私は、特定の科学的見解だけでなく、科学によってもたらされた人類の英知と技術力による新たな進歩の影響を広い意味で探求すべく努めてきました。とりわけ、原子物理学、宇宙論、生物学、心理学については、長い年月をかけて探求してきました。これらの分野における私の理解はかぎられていますが、それでも今のような理解を得たのは、惜しみなく時間を分かち合ってくれたカール・フォン・ワイツゼッカーとデヴィッド・ボームのおかげです。私にとってこの二人は、量子物理学の師です。そして生物学、とりわけ神経科学はロバート・リヴィングストンとフランシスコ・ヴァレーラから学びました。また、マインド・アンド・ライフ・インスティチュート(心と生命研究所)の後援を通じて、数多くの卓越した科学者たちと対話を行なうという恩恵を授かったことにも感謝しています。マインド・アンド・ライフ・インスティチュートは「心と生命会議」という近代科学と仏教科学の対話の場を提供してくれて、第一回目は私が住むインドのダラムサラで1987年に行なわれました。それ以来、「心と生命会議」はずっと続いていて、最近ではまさに今週、ここ、ワシントンで開催されたばかりです。皆さんのなかには、「仏教の僧侶が科学にこれほど強い関心を持つとはいったいどういうことだろう。古代インドの哲学であり、宗教的伝統である仏教が、現代科学と共有する関係とは何だろう。神経科学のような科学の専門分野が仏教の伝統と対話を行なって、いったい何になるのだろう」と、不思議に思われる方もおられるかもしれません。
仏教の瞑想という伝統と現代科学は、その歴史、知識、文化的ルーツは異なるものの、根源的には共通性があると私は考えています。とりわけ、その土台である哲学的見解や方法論には共通性があると思います。哲学的なレベルでは、仏教、現代科学ともに絶対的な概念というものを強く疑います。たとえば、「たましい」のようなものを超越した存在として、または永遠かつ不変の本質として、あるいは実在の根底として概念的に説明づけることができるかどうかといったことです。仏教も科学も、自然界の原因と結果の法則に基づく複雑な相互関係によって宇宙や生命の進化、出現について説明することを優先します。どちらも方法論的な観点から、論理的な実証の役割を重視しています。たとえば、仏教の伝統的な検証方法には、経験、理由、証明という三つの認識された知識の源がありますが、最優先されるのは経験という証拠であり、次に優先されるのが理由、証明は最後にきます。これはつまり、仏教の検証では、少なくともその原則においては、経典がいかに深く尊ばれていようとも、経験に基づく証拠が経典に勝るということです。理由、あるいは推論から導き出された知識の場合も、最終的な正当性は経験に基づく事実の検証から導き出さねばなりません。そして私はこのような方法論に基づく観点から、たびたび仏教徒の仲間たちに「経験的に裏づけられた現代宇宙論や天文学の洞察に基づいて、古代仏教のテキストにある伝承的宇宙論の多くの面を修正しなければならない。場合によっては退けていかざるを得ないこともある」と述べてきました。仏教の現実検証の土台にある第一の動機は、苦しみを克服し、人としてあるべき状態を完成させることにあります。ゆえに仏教の検証では、人間の心と、心が持つさまざまな機能を理解することを第一としてきました。ここでの前提条件は、人間の心にたいする深い洞察を得ることによって、思考や感情、それらの傾向といったものを変容させる方法を見いだし、その結果、より健全で満足のいくあり方を見いだすことです。このような脈絡において、仏教の伝統は人間の心の状態を実に豊かに分類し、特定の心の性質を磨くための瞑想による手法を考案してきました。そこで私は、仏教と現代科学が蓄積してきた知識と経験に基づく情報を真摯な態度で交換することは、人間の心にかんする幅広い問題にかかわることであり、認識や感情、人間の脳に内在する変容能力の理解に至るまでじつに興味深く、かつ有益な可能性があると考えてきました。私自身の経験では、脳の可塑性はもちろん、ポジティブな感情とネガティブな感情、集中力、想像力が持つ性質や役割に関する疑問点について、神経科学者や心理学者と対話を行なってきたことで実に豊かな考えかたができるようになったと感じています。生後数週間の新生児にとって、やさしく抱いてもらうというシンプルな肉体的接触が、新生児の脳の成長に欠かすことのできない重大な役割を果たしていることについて、神経化学と医学は有無を言わさぬ根拠を提示しています。このことは、思いやりと人間の幸福が深くつながっていることを痛感させてくれます。
仏教は長年、人間の心にはすばらしい変容の可能性が本来的に備わっていると主張してきました。そしてこれが、仏教の伝統が瞑想の手法、あるいは瞑想の修行を幅広く発展させてきた理由です。その主な目的は、慈悲の心を培うことと現実のありようを深く洞察する智慧を培うことの二つであり、智慧と慈悲を結び合わせて修行するべきことが仏教の教えの中で説かれています。これらの瞑想修行では、二つの手法がカギとなります。ひとつは集中力を磨き、それを持続させる手法、もうひとつは感情をコントロールして心によき変容をもたらす手法です。この二つの手法には、仏教の瞑想という伝統と神経科学が共同研究の対象とするに値するすばらしい可能性があると私は考えています。たとえば、現代神経科学は、集中力と感情に関連する脳のメカニズムを深く理解することによって発展してきました。一方で、仏教の瞑想という伝統には、心を訓練する実践に関心をよせてきた長い歴史があり、集中力を磨き、感情を整えて、よりよく変容させていく実用的な手法を提供してきました。したがって、現代の神経科学者と仏教の瞑想修行者による会議は、特定の心の作用に不可欠とされてきた意図的な心の活動が脳回路に与える影響について研究する可能性に結びついていくかもしれません。少なくとも、様々な学問の分野にまたがるこのような会議は、多くの重要な学問の分野にとって重大な疑問を提起するのに役立ちます。たとえば、感情や集中力を調整する能力は、各個人に定められた限界があるのでしょうか? それとも仏教が主張しているように、これらの機能と結びつく行動と脳のシステムが提示するようなレベルに修正が可能なのでしょうか? 仏教の伝統である瞑想が重要な貢献を果たせると考えられるもののひとつに、慈悲の心を育む訓練をするための実用的な手法があります。心の訓練に関しては、集中力や感情の調整に、特定の手法がもたらす効果が早いか遅いかなど時間的な影響があるかもしれず、あるならば、年齢や健康状態、その他のさまざまな要素によって、各個人にピッタリ合ったオーダーメイドの手法を新たに作ることができるかどうか、といった疑問の提起が不可欠となるでしょう。しかし、注意を喚起する声もあります。仏教と神経科学のように、根本的に異なる検証方法を持つ伝統が共に対話を行なうときは、異なる文化や学問分野の垣根を越えて意見を交換する際に生じる問題があるものであり、それは避けようのないことです。たとえば、私たちが「瞑想の科学」というとき、それが正確に何を意味するのかということを敏感に察知していなければなりません。科学者の側にしても、「瞑想」という重要な用語が持つ科学の伝統における言外の意味に敏感であることは大切なことです。たとえば、仏教の伝統では「瞑想」のことをサンスクリット語で「バーヴァナ」、チベット語で「ゴム」といいます。サンスクリット語の「バーヴァナ」には、特定の習慣、あるいはありようを培うというような、「養う、育む」という概念が言外に含まれており、一方で、チベット語の「ゴム」には、「習慣性を養う、慣れ親しむ、心に馴染ませる」という含蓄があります。そこで簡潔に述べると、伝統的な仏教の脈絡における「瞑想」は、意図的な心の活動のことを指し、そこには瞑想の対象に慣れ親しんで習慣性を養い、選択した対象や事実、主題、習慣、見解、ありようなどと自分の心が共にある、という意味が含まれます。大まかに言えば、瞑想の実践には二つのカテゴリーがあります。ひとつは心を鎮めて一点に集中させる「止」の瞑想、もうひとつは理解の過程を洞察する「観」の瞑想です。どちらの瞑想の場合も、さまざまに異なるかたちがとられます。たとえば、無常について瞑想するなど、何かを認識の対象として瞑想するかたちをとる場合もあれば、他者の苦しみを和らげたいという心からの利他的な望みを深めることによって、慈悲など特定の心の状態を培うというかたちをとる場合もあります。あるいは、想像というかたちをとって、人間の心が創り出すイメージの可能性を探求する場合もあります。これは心に幸せを培うためのさまざまな方法に用いることができます。ですから、共同研究に取り組む際には、検証対象となる瞑想のかたちが何であるかを認識しておくことが不可欠であり、そのようにすることで、検証中の瞑想修行の複雑性と科学的研究の高度な知識が適合します。
もうひとつ、科学者の側に求められる重要なことがあります。それは、仏教思想の経験的側面と瞑想修行を、瞑想修行に関連する哲学的あるいは形而上学的な憶測と区別する能力です。言い換えれば、科学的アプローチにおいて理論上の仮説と実験に基づく経験的観測、それに続く解釈が区別されなければならないように、仏教においても哲学的仮説と経験に裏づけられた心の状態の特徴、それに続く解釈を区別することはきわめて重要です。そしてこのようにすることで、対話を行なう双方が、経験上観察可能な事実としての人間の心、という共通の場を見いだすことができ、学問分野の枠組みを他方のそれに還元したいという誘惑にかられることもありません。仏教と科学という二つの検証方法を持つ伝統では、哲学的な前提やそれに続く概念的な解釈が異なる場合があります。経験に基づく事実として考えられるかぎりは、それをどのように描写するかにかかわらず、事実は事実のままとしなければなりません。意識の究極的な性質についての真実が何であれ、物理的な過程に究極的に還元できようができまいが、私たちの知覚、想念、感情など経験に基づく事実のさまざまな側面について、私たちはその理解を共有することができると考えています。私は、仏教と科学という二つの異なった検証方法を持つ伝統が、このような考慮をしつつ、ともに緊密に協力し合うことで、私たちが「心」と呼ぶ内なる主観者の経験が織りなす複雑な世界を理解するために、真の貢献ができると考えています。このような共同研究の成果は、すでに現れはじめています。準備段階の報告書によると、定期的に行なう簡単な注意深さ(憶念)の実践、あるいは仏教において発展してきた慈悲の心を培うための心の訓練がもたらす効果は、ポジティブな心の状態に関わる観察可能な変化をヒトの脳に生じさせることによって測定することができます。最近の神経科学の発見は、生来、脳には可塑性があり、シナプス(神経細胞の接合部)の結合も、新たなニューロンの出現も、自発的に行なう運動や環境の強化など外的な刺激にさらされた結果であることを証明しています。仏教の瞑想という伝統が、神経の可塑性にかかわる心の訓練の種類を提案することで、この科学的調査の分野の拡大に役立つ可能性もあります。仏教の伝統が暗示しているように、心の訓練が観察可能な脳のシナプスおよび神経の変化に影響をおよぼすことが明らかになれば、これは広範囲にわたるかかわりが出てくる可能性があります。このような研究の影響は、人間の心にかんする私たちの知識を際限なく広げていくでしょう。しかし、より重要なのは、このような研究の影響が、教育や心の健康を理解していく上できわめて大きな意味を持つ可能性があることではないでしょうか。同様に、仏教の伝統について述べるなら、慈悲の心を培うことは、一人ひとりのものの見方を根本的に変えることにつながり、他者への共感の深まりにもつながります。これは社会全体に大きな影響をおよぼす可能性があります。
最後に、私は、神経科学と仏教の瞑想という伝統の共同研究が、倫理と神経科学に介在するきわめて重要な探求に新たな光を投げかけてくれるものと信じています。倫理と科学の関係について人がどんな概念を持っているかにかかわらず、科学はその実践において、道徳的には中立に、価値判断に影響されないスタンスで、経験に基づく学問の分野であることを第一に発展してきました。そうして科学は、私たちが経験することのできるこの世界や自然の法則の根底にある詳細な知識を明らかにするための調査の方法として、本質的に認識されるようになったのです。純粋に科学的な視点だけで見るならば、核兵器の発明はじつにおどろくべき達成です。しかし、核兵器の発明には、死と破壊という想像を絶するような苦しみを負わせる力があるので、これは破壊的な発明ということになります。これは何が善で何が悪かに基づいて決めなければならない倫理的評価です。最近まで、倫理と科学を分けて考えるこのようなアプローチは、人間の道徳的思考能力は知識とともに発達するものである、という理解とともにうまくいっていたかのように見受けられました。しかし現在、その人間性は重大な岐路にあります。神経科学、とりわけ20世紀終盤の遺伝学の急進的な発展は、人類の歴史を新しい時代へと導きました。私たちは、遺伝子操作のために提供された技術による科学の進歩が、人間の脳やからだの細胞の遺伝子レベルで、途方もない倫理的問題をもたらすことを理解する段階に到りました。このような知識と力を得たことによる急速な進歩に、私たちの道徳的思考がついていくことができなかったことはあまりにも明白です。それでも、このような新たな発見によって派生する問題やその応用は、人間性の概念そのものや、人類という種の保護にきわめて広範にわたる影響をおよぼします。したがって、「科学的知識を深めて技術力を高めることは社会全体としての責任であり、その知識と力を何に使うかという選択は個人の手にゆだねられるべきである」という見解はもはや適切ではありません。とりわけ生命科学においては、根本的な人道主義と倫理的な考慮が科学的発展を方向づけていくような方法を見つけなければならないと思います。私は、根本的な倫理原則を引き合いに出すことによって、宗教的倫理と科学的探究の融合を主張しようとしているのではありません。むしろ、私が「世俗の倫理観」と呼ぶものは、慈悲、寛容、やさしさ、思いやりといった倫理原則のカギであり、責任を持って知識と力を使うことは、宗教を信じる者と信じない者、この宗教の信者か、あの宗教の信者か、などの垣根を越えた原則なのです。個人的に私は、科学を含めた人間のすべての営みが、手のひらの指一本一本であると想像するのが好きです。それぞれの指が、基本的な人間らしい共感や利他の心という手のひらにつながっているかぎり、この手の指は人間の幸福のために働いて役立ってくれるでしょう。私たちは、真にひとつの世界に生きています。環境問題はもちろん、現代の経済、電子メディア、国際観光などのすべてが、日常生活の中で私たちがどれほど深く今の世界とつながっているのかを気づかせてくれます。このように互いにつながり合った世界において、科学の世界はきわめて重大な役割を担っています。歴史的理由が何であれ、こんにち、科学者は社会において絶大な信頼と敬意を享受しています。それは、私が哲学や宗教の修練において享受するものよりもはるかに絶大です。私は、科学者の方々にたいし、その専門的職業を、人間として誰もが共有する根本的な倫理原則が命ずるところへと昇華させていただくようお願いしたいと思います。
Copyright 2005 Mind and Life Institute, Boulder, CO, USA. All rights reserved.