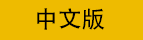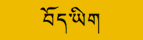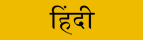インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ
早朝より、ダライ・ラマ法王公邸の向かいにあるツクラカンでは、各地から集まった参加者が法王のご到着を待っていた。法話会の参加者およそ7,000人のうち、450人は主にラホールとスピティのヒマラヤ地方から、青年仏教会(Young Buddhist Society)のメンバーである350人はウッタル・プラデーシュ州、ビハール州、ラジャスタン州から、30人はタミルナドゥ州から、そして400人がその他のインドの州から来ている。さらに78カ国から1,700人の外国人、1,500人のチベット人僧侶と尼僧、3,500人の一般のチベット人も法話会に参加した。
今回の法話会はナーランダー・シクシャ(Nalanda Shiksha)の主催によるもので、同団体は法王のご友人でもあり、あるあらゆる真正な仏教の伝統に基づく著名な指導者の下で仏教を学んできた。そして、ナーランダー僧院の伝統では欠くことのできない聞・思・修の修行体系を現代のインドで生きた教えとして伝承していくことに関心を持っている、と宣言している。ナーランダー・シクシャは、過去に法王の法話会を2012年と2013年にダラムサラで、2014年にムンバイで、2015年にサンカーシャで主催しており、今回で5回目となる。法王は同団体の要望に応え、インドの学者たちの手による重要なテキストとなっているカマラシーラ(蓮華戒)の『修習次第』とシャーンティデーヴァ(寂天)の『入菩薩行論』の解説をしてこられた。ナーランダー・シクシャは、仏教のすべての学派や相承系譜に対する偏見を持たず、すべての仏法とその真正なる伝統、その導師たちに仕えることを使命としている。

|
法話の始めに、ダライ・ラマ法王にインドの伝統的な供物を捧げるヒマラヤ地方の仏教徒。2016年6月7日、インド、ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
法王が法座に座られると、インドの上座部仏教の僧侶たちが吉祥経をパーリ語で唱えた。続いてナーランダー・シクシャを代表して、ヴィーア・シン氏が法王にインドの伝統に基づく供物を捧げる儀を執り行なうことを宣言すると、順次、飲み水・洗足水・華・香・灯明・香水・献食・音楽の8種の供物を載せた盆が法王の元に運ばれ捧げられた。
法王は次のように述べられた。
「私たちも密教の儀式でこのような供物を捧げます。これを見て、仏教はインドの伝統なのだと改めて感じています。今日のインドには仏教を遠い過去の遺産と捉える人たちもいれば、アンベードカル博士の教えに従い、仏教を新たに取り入れた人たちもいます」
「インドで誕生された釈尊の教えは、その後、偉大な学問寺であったタキシラ、ヴィクラマシーラ、ナーランダーの各僧院に受け継がれていきました。そして、8世紀にチベットの仏教王ティソン・デツェンによってチベットに招聘されたシャンタラクシータ(寂護)は、雪の国チベットにナーランダー僧院の伝統を伝え、広めててくださいました。それ以来、チベット人はこの伝統を1000年以上守ってきました。歴史的に見て、あなた方インド人は私たちの師匠にあたりますが、その後は弟子である私たちチベット人がこの伝統を絶やさずに維持してきたのです。ですから今日こうして皆さんとこの伝統を共有できることを、私は大変感慨深く感じています」
法王は聖者の地インドについて、千年以上ものあいだ世界の主要な宗教が繁栄してきた特別な国であると述べられた。インドには、サーンキヤ学派、ジャイナ教、仏教などインド古来の伝統があり、のちにゾロアスター教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が入ってきてそこに加わった。そして、このすべての伝統が互いの立場を尊重し合い、調和を保って共存しているインドは、他者が見習うべき模範であると法王は言われた。さらに、仏教をはじめ古代から引き継がれてきたインドの伝統は、分析と考察を重ねることを重視しており、それが人間の心と感情の働きについての深い理解をもたらしたのである。その知識には、現代にも通用する実用的な価値があることから、現代人の関心を呼ぶものとなっている。
法王は、宗教には神という創造主の存在を受け入れている有神論のグループと、神の存在を受け入れず、因果の法を信じる無神論のグループがあることを説明された。しかしどちらのグループも、愛と慈悲の心を高め、寛容さ、知足、自己規制などの資質を育むことの重要性を説いている点ではまったく同じである。これらの共通した教えは、過去、現在、未来を通して私たち人間に恩恵をもたらすものであり、たとえ哲学的な見解は違っていても、すべての宗教が同じように愛と慈悲の実践を説いているのだから、異なる宗教間の調和を図ることが重要である、と法王は述べられた。

|
ダライ・ラマ法王の法話に聞き入るインド人仏教徒たち。2016年6月7日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
「『四つの聖なる真理』(四聖諦)は釈尊のユニークな教えであり、因果の法に基づいて、最終的に一切有情を永続する幸せの境地に導いていくものです。釈尊は、創造主としての神の存在も、それ自体の側から成立する自我の存在も受け入れませんでした。釈尊の後に現れたナーガルジュナ(龍樹)、アサンガ(無着)やその弟子たちは、釈尊の教えに関する注釈書をサンスクリット語で書かれました。やがて釈尊のお言葉はチベット語に翻訳され、100巻のカンギュル(経典。釈尊が説かれた教え)と220巻のテンギュル(論書。経典の注釈書)が誕生しました」
「チベットではこれらの経典と論書を基にして、仏教哲学、サンスクリット語、論理学、医学、美術工芸学からなる主要5科と、文法・語句などの副次5科による学問の分野を修学する伝統が維持されてきました。私は家庭教師の先生からサンスクリット語の文法を学びましたが、その知識はすでに空となって消えてしまいました」
法王は、途中休憩の時間を主催者グループの人々との質疑応答に当てられた。最初の質問は死についてのものだった。法王は、釈尊が四聖諦の教えを理解するために無常について説かれたことを述べられて、無常には一瞬ごとに変化する微細なレベルの無常と、花が咲いて、萎れて、枯れてなくなるというような目で見ることのできる粗なレベルの無常があることを説明された。そして毎日死について考え、瞑想することが精神修行の役に立つと述べられた。また、密教の修行では、死を迎える過程として、意識が次第に微細なものになっていく8つの段階の観想を毎日行なうことにより、死が現実に訪れる時の準備をすることができるとして、ご自身もそれを実践されていることを語られた。
最後に法王は、「死は人生の一部なのですから、私たちはそれを受け入れなければなりません」と言われた。
別の質問者は僧侶の袈裟についてお尋ねし、法王は、一般的に袈裟の色は青、赤、黄色であるべきで、黒や白ではいけないと答えられた。赤い袈裟はチベットのように寒い気候により適しているのに対し、タイ、スリランカ、ビルマの僧侶はサフラン色の袈裟を着ると説明された。また、どんな色にも関わらず、袈裟は布切れを継ぎはいだものであること、一人の僧侶が所有できる袈裟の数は1つであること、仮にそれ以上所有するならそれは僧院に属すると考えるべきことを述べられた。同様に、僧侶が所有できるものには13の物品があり、それらを加持する手順も定められている。
そして法王は、ヒマラヤ地方とナーランダー僧院の伝統との関係について次のように語られた。
「私は仏教の重要な教えを、ヒマラヤ地方出身の先生方から授かりました。クヌ・ラマ・リンポチェからは『入菩薩行論』の教えを、ゲシェ・リグジン・テンパからはツォンカパの『善説金蔓』の教えを授かりました。最近ではおよそ400人のヒマラヤ地方出身の僧侶が僧院で修学しており、そのうちの多くがいずれ指導者の立場となるでしょう」
「ヴァスバンドゥ(世親)は、釈尊の教えには、経典の教えと実践に基づく理解による教えの2種類があると述べています。この2つは勉強と実践を通してのみ享受できるものです。経典の教えとは経典に述べられている教義を与え、授かること、実践に基づく理解による教えとは、三学の実践を積むことで得られる理解を意味します。ヒマラヤ地方出身の人たちは、僧侶に限らず、尼僧も在家信者もできる限り勉強と実践をするように努めなければなりません」
「私たちが『三宝に帰依いたします』と唱える時、三宝とは何なのか、その因は何なのかを理解する必要があります。またそれらの理解は理由に基づくものでなければなりません」

|
|
シャーンティデーヴァの『入菩薩行論』の解説をされるダライ・ラマ法王。2016年6月7日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
法王はシャーンティデーヴァの『入菩薩行論』を手に取られ、シャーンティデーヴァが8世紀にこのテキストを記されてから現在に至るまで、これよりもすぐれた菩提心を育むための書は未だ現れていない、というクヌ・ラマ・リンポチェが言われたことを繰り返された。
「シャーンティデーヴァの『自分と他者を入れ替えて考える』という菩提心を育むための教えの源は、ナーガールジュナの『宝行王正論』と、『秘密集会』(グヒヤサマージャ)の根本経典にある大日如来のお言葉に関する解説書である『菩提心の解説』にあります。そしてナーガールジュナのこの教えの源は、『華厳経』と『般若経』です」
「釈尊は悟りを開かれた後、ご自身の深遠なる空の見解を他の人が理解するのは難しいと考えられて、仏法を説かれなかった時期があります。しかしその後、初転法輪において『四つの聖なる真理』、それぞれの真理の4つの特徴(四諦十六行相)、悟りに至るために必要な37の修行について解説した『三十七道品』の教えについて説かれました。その後第二法輪では、霊鷲山において、清らかなカルマを持った弟子たちに対して空の教えを説かれました。つまり、釈尊がまわされた3つの法輪のうち、初転法輪は四聖諦、第二法輪は般若経、第三法輪は仏性と光明の心について説かれたことになります」
法王は、テキストを全部読むのではなく、方便と智慧、そして「二つの真理」の要点に焦点を当てて解説することを伝えられた。私たちはすべての現象を目に映る通りに捉えてしまうが、実際にはその通りに存在しているのではない。この間違った見解によって私たちの心には煩悩が生じる、と法王は説かれた。そして、私たちはふつう利己的な考え方をする傾向があるが、それは他者への思いやりを育むことによって克服することができると説明された。そして法王は、このテキストの第9章には空の見解について説かれているが、これをしっかりと理解するためには他のテキストも読んで勉強する必要があると述べられた。
法話会は引き続き明日も行われる。