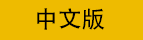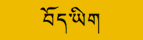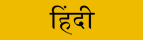インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ
ダライ・ラマ法王によるチベット人学生のための法話会が、本日、最終日を迎えた。3日間にわたる法話会には、3,000名を超えるチベット人の学生たちが参加し、法王から直接教えを授かった。
 |
| 文殊菩薩の許可灌頂を授けるにあたり、準備の儀式を行なわれるダライ・ラマ法王。2016年6月3日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁) |
法話のはじめに、チベット子ども村(TCV)の学生たちが心の科学のテキストに含まれている読誦文を唱えると、法王も共に唱えられた。続いて法王は、文殊菩薩の許可灌頂を授与するための準備の儀式を行なわれた。
法王は菩提心生起の儀式に入られると、「マイトレーヤ(弥勒)の『現観荘厳論』では、“菩提心とは、一切有情を救済するために完全な悟りを得たいと願う心である”と定義づけられています」と述べられて、次のように語られた。
「私たちが自分自身について考えているとき、自分のからだや心、家族や友人に関連付けて“私”というものを感じています。私たち人間は、五蘊という心とからだの構成要素の集まりを支配する者として“私”というものを感じているのです。しかし仏教では、“私”という存在にはそれ自体の力で成立している実体性は微塵もない、と説いています。つまり、それ自体の力で他に依存せずに固有に成立している“私”が存在するという考えを否定しているのです」
「自分のことだけを考えていると、自分を不幸にしてしまいます。逆に、心を開いて他の人たちのことも考えるならば、恐れや不安から自由になることができます。自分と同じようにすべての有情が苦しみを避けたいと願っていることに思いをはせるならば、利己的なものの考えかたは少なくなっていくでしょう。皆さんの周りにいる人たちを観察してみてください。すると、他の人たちのことを考えて行動している人は、自己中心的な考えかたをしている人たちよりもずっと幸せな場合が多いのです。たとえば、おいしいお菓子を手に入れたとしたら、それを分かち合って食べている人と一人占めしている人とでは、どちらが幸せでしょうか?」

|
ダライ・ラマ法王のお話に熱心に耳を傾ける3,000名を超える生徒たちの一部。2016年6月3日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
「皆さんはチベット人です。そして若いのですから、他の人たちのことにも思いを広げてください。その思いをチベット本土の600万人の人々に、さらにはアジア全体の人々に、そして世界中の生きとし生けるすべてのものたちへと広げてください。菩提心とは、一切有情を救うために完全な悟りを得たいと願う心のことです。他の有情を利益することができますように、そのために仏陀の境地に至ることができますように、という二つの熱望を兼ね備えた心が菩提心と呼ばれるものなのです」
法王は、40年あるいは50年前は菩提心のすばらしさは実感していたものの、実際に培うことはきわめて難しいと感じていた、と述べられた。しかし、1967年にクヌラマ・リンポチェから『入菩薩行論』の解説を含めたテキストを伝授され、その時リンポチェからこの教えを説く機会をできるだけ多く持つよう勧められた。以後、菩提心に対する理解が徐々に深まるにつれて、菩提心がより身近なものに感じられるようになった、と法王は述べられた。
シャーンタラクシタ(寂護)は、鋭い知性を持つ者たちは最初に空の理解を育み、これを支えとして菩提心を培うべきである、と述べておられるが、法王もこのようにして菩提心を培ってこられた。法王は、「20代の頃から空について考えてきましたが、最終的に大切なことは、空の理解と菩提心を結びつけていくことです」と述べられて、チャンドラキールティ(月称)の『入中論』から次の偈を引用された。
- 世俗〔の真理〕と究極〔の真理〕という白い二つの翼を広げ
- 白鳥の王は群れを率いて
- 徳の風の力により
- 勝利者〔仏陀〕の徳の大海の最勝なる彼岸へと飛んでいく

|
立ち上がって菩提心生起の儀式に参加する生徒たち。2016年6月3日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
菩提心生起の儀式の中で、法王はラサのツクラカンに安置されていた聖観自在菩薩像にまつわる話をされた。ある晩、法王は特別な自生の聖観自在菩薩像のまわりを右繞している夢をご覧になった。「もっと近くに来なさい」と聖観自在菩薩像が法王を呼ぶ声がしたので身を寄せてみると、聖観自在菩薩像が喜びとともに努力を維持するための偈を唱えておられるのが聞こえてきた。法王は、夢に現れたこの聖観自在菩薩像は文化大革命によって破壊されてしまったが、のちにその破片の一部が亡命下の法王の元に届けられたことを語られた。法王はそれを千手千眼聖観自在菩薩像の中に納め、今、ダラムサラにあるナムギャル寺に安置されたのである。
「この千手千眼聖観自在菩薩像は、いずれは中に納めた聖観自在菩薩像の破片を取り出して、われわれと共にチベットに帰還できるようにと考えて建立したのです。その時が来たら、皆さんも一緒にチベットに帰りましょう」
続いて法王は、パンチェン・ラマ4世テンパ・ニマ(1781 − 1854)が編纂された『リンジュン・ギャツァ』という儀軌次第集にある儀軌に基づいて文殊菩薩の許可灌頂を授与された。そして、ドムトンパの『自らの心の連続体を励ます信心の木』の詩頌を最後まで読まれた。

|
3日間にわたる法話会の終わりに、ダライ・ラマ法王に謝辞を捧げるTCVのグドゥップ・ドルジェ校長と供物を奉納するために列をつくるTCVの職員たち。2016年6月3日、インド、ヒマーチャル・プラデーシュ州 ダラムサラ(撮影:テンジン・チュンジョル、法王庁)
|
終わりに法王は、あるアムドのラマの話をされた。その博識な高齢のラマは、ある村の人々から説法に来てほしいと招待された。ラマが、「私はそちらへ伺うにはあまりにも年を取りすぎています」と答えると、村人たちは「祝福をいただくだけでもかまいませんから、どうか来てください」と言って譲らなかった。ラマは村に赴き、長い教えを完全に最後まで説くと、こう言った。「私は、この手を皆さんの頭の上に置いて祝福を与えるだけで解脱に導くことができるような人間ではありません。私にできるのは、皆さんが仏陀の教えを理解できるように教えを説くことだけなのです」
続いてチベット子ども村の管理職にある職員たちが、法王に供物を捧げるために列をつくり、仏像や113枚の無量寿仏(阿弥陀仏)の祈願文を奉納した。チベット子ども村のグドゥップ・ドルジェ校長が謝辞を捧げ、聖観自在菩薩が立てられた「雪の国チベットの人々を守護する」という誓願は、今、法王が私たちを守ってくださっているように、歴代のダライ・ラマに今日まで引き継がれてきたことを讃えた。そして感謝の念を述べるとともに、法王のご長寿を祈念した。
法王は、微笑んで合掌されると、「また来年会いましょう」と述べられた。