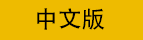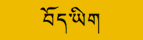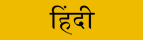和歌山県 高野山
昨日とは対照的な明るい朝空の下、ダライ・ラマ法王は早朝高野山大学松下講堂黎明館に向かわれた。今日の午後行なわれる「チベット密教 胎蔵マンダラの灌頂」を弟子たちに伝授するために、阿闍梨(ラマ)が本尊として生起する儀式をご自身で行われるためである。
 |
| 高野山大学松下講堂黎明館で「チベット密教 胎蔵マンダラの灌頂」の準備の儀式を執り行われるダライ・ラマ法王とナムギャル寺の僧侶たち。2014年4月14日、高野山(撮影:ジェレミー・ラッセル、法王庁) |
 |
| 高野山大学松下講堂黎明館で前行法話をされるダライ・ラマ法王。2014年4月14日、高野山(撮影:ジェレミー・ラッセル、法王庁) |
第一偈の冒頭で、法王は次のように述べられた。
「他者を慈しむとは、他者を劣った者として見下すことではありません。また、自分より他者の方が大切であると考えることでもありません。世俗的な幸せや成功はすべて他の有情たちに依存して生じるのだということを認識しておかねばなりません。来世におけるより幸せな転生も、他の有情たちに依存して達成されるものです。一切智の境地もまた、他の有情たちに依存して達成されます。私たちはなぜ、仏陀たちを尊ぶように他の有情たちを尊べないのでしょうか。これについてチャンドラキールティは、「生きとし生けるもの(有情)に対する慈悲とは、種(因)であり、収穫(果)である」と述べておられます。有情に受けた深い恩を思い、有情に対して心から感謝し、最もすぐれたものとして慈しまなければなりません。」
また法王は、言葉によって他のものを排除している可能性がないか、考えてみる必要があると述べられた。
「私は、釈尊の弟子として、僧侶として、ナーランダー僧院の正当なる伝統を引き継ぐ者として、自分にこう言い聞かせています――“他者を慈しめないならば、自分を誰よりも劣った者として考えよ”と。 私たちは煩悩に支配されているため、ものの実体にとらわれて、自分を誰よりも大切にしようとします。第4偈の“悪い性質を持った有情たち”には、病に苛まれている人たちも含まれますので、そういう人たちこそ、心から慈しまなければなりません。」
そこで法王は、先日、インドのデリーにある癩病患者の診療所を訪問されたこと、その診療所では笹川さんという日本人が病に苦しむ人々を支えていることについて述べられた。
 |
| 高野山大学松下講堂黎明館でダライ・ラマ法王の法話を聞く受者たち。2014年4月14日、高野山(撮影:ジェレミー・ラッセル、法王庁) |
「このような病に苦しんでいる人たちは、多くの場合汚名を着せられ、疎外されています。私は、インドの役人たちに、彼らも私たちと同じ人間だと言いましたが、今なお疎外され続けています。」
「私たちを侮辱するなど、ひどい目にあわせた相手を慈しむのは容易なことではありません。大切なのは忍耐を訓練することです。ですからその人のことを、忍耐を修行するための貴重な機会を与えてくれた恩師と考えるならば、その人のことが有り難く思え、感謝できるようになるでしょう。」
法王は、「自分と他者の立場を入れ換えて考える」という菩提心を育むための修行法について次のように説明された。
「母なるすべての有情たちに利益と幸せを捧げ、母なるすべての有情たちの被害と苦しみをみな密かに私が引き受けられますように」という祈願によって、実際にすべてのものを救えるわけではありません。しかしそのような心の持ち方をすることで、勇気と自信を持てるようになるのです。」
「最後の偈は、賞賛されたい、報酬を得たいなど世俗的な考えに影響されて修行を汚してはならない、という教えです。その対策として、すべての物事を幻のように見て、その執着から離れるべきことを教えているのです。釈尊は、第二法輪において空の教えを説かれ、五蘊をはじめとする人以外のすべての現象もまた、人の自我と同じように、実体のない空の本質を持つものであると述べられています。なぜならすべての現象には実体がないにもかかわらず、あたかも実体があるかのように現れてくるからです。このような現われは、怒りや執着が生じる土台となるものなので、実体を持って存在しているかのような現われは否定されなければなりません。私たちが煩悩にまみれているのは、すべての現象の究極のありように無知だからです。つまり私たちは、無知を滅することによって、すべての煩悩を克服することができるのです。」
「ゲシェ・ランリタンパがこの教えで強調しておられるのは、菩提心の実践です。これらの八つの偈と昨日説明したツォンカパの『帰敬偈』を暗唱し、その教えを日々の生活に活かしていくとよいでしょう。さて、そろそろ正午です。からだに力を補給することにしましょう。」
 |
|
高野山大学松下講堂黎明館で行なわれたダライ・ラマ法王による「チベット密教 胎蔵マンダラの灌頂」の儀式中お加持を授かる高野山大学の教職者たち。2014年4月14日、高野山(撮影:ジェレミー・ラッセル、法王庁) |
また真言(マントラ)には、心を守護するもの、心をごく普通の現われから守護する、という意味があります。
『チベット密教 胎蔵マンダラの灌頂』は行タントラに属します。私はこれをリン・リンポチェからダラムサラのナムギャル寺で伝授していただきました。その目的は、一切有情の究極的な救済の実現にあります。ですから菩提心を培い、空を理解する智慧を育むことが大切なのです。」
法王は最後にこのように述べられて、金剛峯寺に戻られた。明日、法王は再びこの高野山大学松下講堂黎明館で講演を行なわれ、参加者からの質問に答えられた後、東京へ移動される。